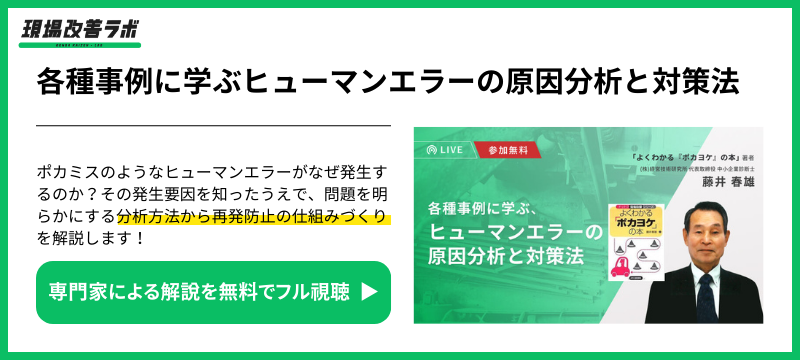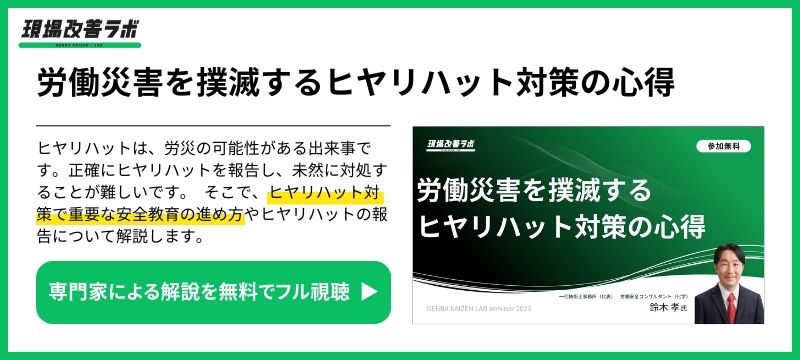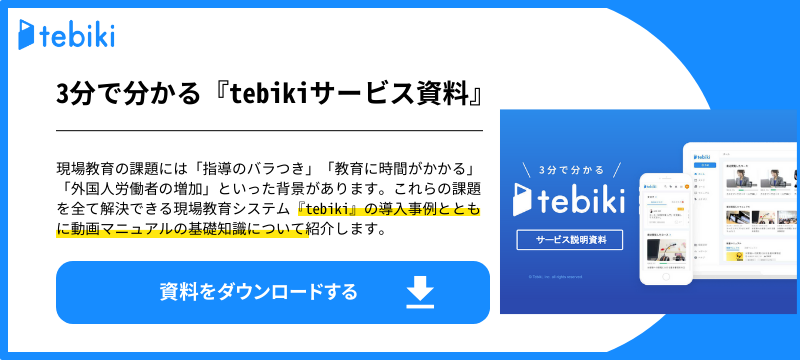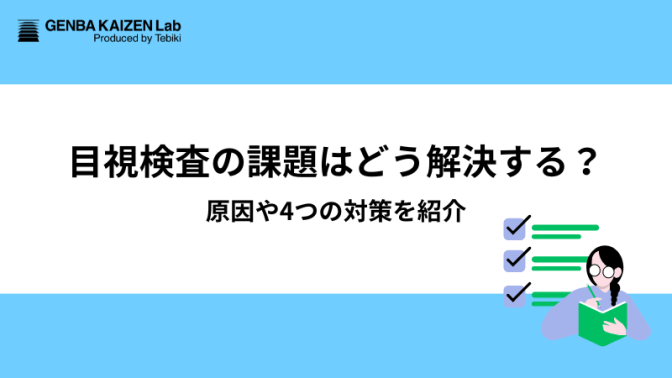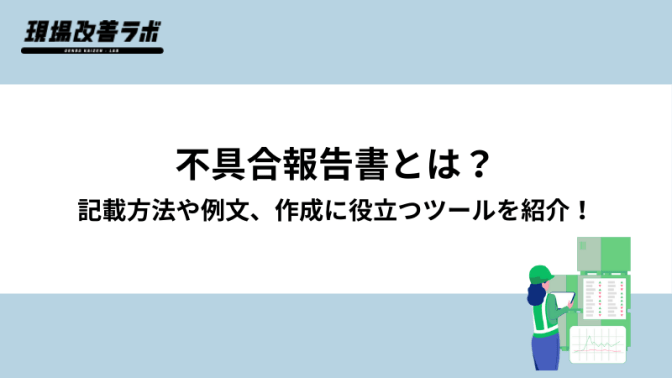人が作業を行う場合には、常にヒューマンエラーの発生を考慮する必要があります。ヒューマンエラーを放置してしまうと、同じ作業をやり直したり、後工程に迷惑をかけ大きな損失を受けたりすることがあります。
この記事では、ヒューマンエラーの概要とヒューマンエラーが発生する原因、その対策について解説します。ヒューマンエラーについて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
他にも現場改善ラボでは、ヒューマンエラーが発生する要因や、課題を明らかにする分析手法から再発防止の仕組みづくりまで中小企業診断士の藤井 春雄 氏が解説している動画を無料で視聴できます。ヒューマンエラーについて網羅的に解説しておりますので、是非ご覧ください。
目次
ヒューマンエラーとは?簡単に解説
ヒューマンエラーとは、人間による行動を起因として発生した失敗や事故のことです。日本産業規格(JIS Z 8115:2000)では『意図しない結果を生じる人間の行為』と表現されています。
人間はミスをする生き物であるため、これまでの生活や仕事の中でミスをしたことがない人はいないでしょう。
特に製造業の現場では、複数人が関与してさまざまな作業工程を行うことが多く、すべての人がミスなく完璧に仕事をこなすための仕組みづくりが必要です。。また、ヒューマンエラーが発生してしまった際の影響を最小限に抑えるために、ヒューマンエラーの発生を速やかに検知する工夫を施すことも効果的です。
ヒューマンエラーの意味とは?
ヒューマンエラーとは、人間による行動を起因として発生したミスや事故のことです。ヒューマンエラーは注意不足から発生するケアレスミスなどの小さいものから、企業に深刻な影響を及ぼすような大きいものまで様々な種類があります。
ヒューマンエラーに含まれないミス
人間の行動によって起こってしまうミスや事故はヒューマンエラーに含まれます。一方で、機械トラブルは人間の行動が原因ではないため、ヒューマンエラーに含まれません。例えば、機械の老朽化や消耗などによって発生するミスや外部委託で作成されたマニュアルに従って発生したミスはヒューマンエラーには含まれません。
ただし、社内でマニュアルを作成しているにもかかわらずミスが発生してしまった場合は、マニュアル作成時に内容の記入漏れや記載すべき内容を十分に検討できていないことが原因であることも多く、そのような場合はヒューマンエラーに含まれます。
ヒューマンエラーに近い言葉
ヒューマンエラーに近い言葉として「人為的ミス」や「人災」があります。人為的ミスとは、業務を行う際に誤った判断や行動を起こしてしまうことによって発生するミスを指します。人為的ミスは操作ミスや、手違い、情報の誤解などが該当し、主に不適切な行動やコミュニケーション不足などの経験不足や連絡不足が原因とされています。
人災とは、人間によって引き起こされる災害や災難を指します。これは自然災害とは異なり、主に人為的な要因によって引き起こされる災害です。人災は工業事故や、交通事故、環境汚染などが該当し、人間の誤った行動や判断によって引き起こされる事故を指します。
「人為的ミス」と「人災」の違いとしては、「人為的ミス」は個別の行動や判断に焦点を当て、一般的に小規模な問題や事故を指しているのに対し、「人災」はより広範で、個々の行動だけでなく大規模な組織や社会の過ちによって引き起こされる深刻な災害や事故を指していることが挙げられます。
ヒューマンエラーの2つの分類
ヒューマンエラーは「偶然起きてしまったもの」と「意図的におきてしまったもの」の2種類に分類することができます。ここでは以下2つの種類について詳しく解説します。
- 「ついつい・うっかり」が起こす意図的ではないヒューマンエラー
- 「あえて」が引き起こす意図的なヒューマンエラー
詳しくは、以下の図もご参考下さい。
▼ヒューマンエラーの種類▼

「ついつい・うっかり」が起こす意図的ではないヒューマンエラー
意図的ではないヒューマンエラーは、「ついつい・うっかり」といった行動から生じることがあります。これらのヒューマンエラーは無意識のうちに行われており、心理学的な要因や認知プロセスの影響が大きく関与しています。ここでは意図的ではないヒューマンエラーが生じる以下の原因について解説します。
- 記憶エラー
- 認知エラー
- 判断エラー
- 行動エラー
- 全エラー共通
詳しくは、以下の図も参考にしてみてください。
▼「ついつい・うっかり」が起こすヒューマンエラー▼

記憶エラー
記憶エラーとは、業務内容をきちんと記憶していないことによって発生するヒューマンエラーです。覚えにくい情報や反復、復習しないことによる記憶内容の薄れや変化、思い出す手がかりが不足していることでミスをしてしまいます。
例えば一度学んだ内容を復習しなかったり覚えるべき情報が多すぎると、業務内容の抜け漏れが出てしまい、ヒューマンエラーが発生します。
製造業における記憶エラーの一例として、生産ラインでの部品の仕様や工程の取り違えが挙げられます。業務内容がきちんと定着していないと、作業者が異なる製品の仕様を混同し誤った部品を組み込んでしまう可能性が高まります。
認知エラー
認知エラーとは、情報を誤って認知し、誤った行動をしてしまうことで発生するヒューマンエラーです。
認知エラーが起こる原因として、情報の質の悪さと伝え方の悪さが考えられます。情報の質の悪さについては、誤った情報やあいまいな情報、識別の弱い情報を伝えてしまうことが原因。伝え方の悪さについては、マニュアルの文字が小さかったり、発信者側の声が小さくて内容がちゃんと伝わっていないということが挙げられます。
例えば、製造業の場合だと作業手順を誤って認知してしまい、間違った認識のまま機械を操作してしまうことによって、機械の故障や事故につながります。
判断エラー
判断エラーとは、思い込みから誤った判断をしてしまうことによって発生するヒューマンエラーです。
判断エラーが起こる原因として、状況理解が困難であることが考えられます。目的や目標などの進むべき方向が不明確であったり判断基準の内容があいまいな状況であると、判断エラーを起こしやすくなります。
例えば、製造業の場合、原材料品質のチェック項目が曖昧であると品質が作業者自身の判断に委ねられてしまうため、品質不良が大量に発生してしまう恐れがあります。
行動エラー
行動エラーは、作業内容が身についておらず、方法や手順が不適切である場合に発生します。
行動エラーが起こる原因として、機械の操作方法が自身の操作感覚と合わなかったり、持ちにくい・操作しにくい等の操作性の悪さによって発生します。
例えば、製造業だとマニュアルで見た作業内容と行動が一致しておらず誤った機械操作をしてしまうことで行動エラーが発生します。行動エラーを減らすためには、直接作業をしながら学ぶことのできるOJTや業務作業を可視化できる動画マニュアルによる教育が効果的です。
全エラー共通
上記4つのエラーに共通しているのは、業務において注意力がうまく働いていないということです。注意力がうまく働かない原因として、過度な集中や長時間の集中が要求される場合、注意すべき対象が多い場合、注意を阻害する障壁がある場合が考えられます。
また、作業における疲労やストレスが溜まることで業務における注意力が低下し、ヒューマンエラーの発生に繋がります。
「あえて」が引き起こす意図的なヒューマンエラー
「あえて」が引き起こす意図的なヒューマンエラーとは、慢心により注意を配らずに手抜きをしたり、決まり事を守らず手順を意図的に無視することで起こってしまうヒューマンエラーのことです。
業務に慣れてしまったことで本来すべき確認を怠ってしまい、気付かぬうちにミスが発生してしまうということです。例えば、業務効率を求めてしまったり、めんどくさいという気持ちからチェックを省いたりすることで発生します。「あえて」型のヒューマンエラーは主に以下3つが原因として引き起こされます。
- 職場全体で作業手順を守る意識が不足している
- 決まり事の内容と必要性が理解されていない
- 決まり事の内容や必要性を理解しているものの、納得していない
具体的に製造業における一例として、品質検査を行う際、業務効率を求めるあまり確認を十分に行わないことがあります。品質検査が不十分になってしまうと欠陥部分や不良品を見逃してしまい、品質不良の商品が顧客に届く可能性があります。
関連記事:製造業における品質不良の原因と対策方法は?実際の取り組み事例も紹介!
ヒューマンエラーによって事故が引き起こされた3つの事例
ヒューマンエラーはときに企業にとって深刻な影響を及ぼします。ここではヒューマンエラーによって事故が引き起こされた3つの事例について紹介します。
- みずほ証券のジェイコム株大量誤発注事件(2005年)
- 年金記録5,000万件の不備問題(2007年)
- 新幹線のぞみ34号台車亀裂事件(2017年)
みずほ証券のジェイコム株大量誤発注事件(2005年)
2005年に起きたみずほ証券のジェイコム株大量誤発注事件は、データ入力ミスによるものです。みずほ証券のスタッフが本来の注文として「1株を610,000円で売る」と入力すべき個所に対し、「610,000株を1円で売る」と誤って入力したのが原因です。このミスは、コンピューターシステムの警告を無視してデータを入力したため発生し、注文が完了した後で発見されました。
キャンセルを試みたものの失敗し、この誤発注はみずほ証券に約30億円の損失をもたらしました。本事件は株式市場に大きな影響を与え、みずほ証券自身にも財務的な大きなダメージを与えました。
年金記録5,000万件の不備問題(2007年)
2007年に起きた年金記録5,000万件の不備問題は、日本の社会保険庁でのデータ管理のミスにより発生しました。
当時、マイナンバーのような国民1人1番号という制度がなく、国民年金や厚生年金保険、共済組合などの年金制度によって年金記録番号が異なっていたため、1人の個人に複数の異なる番号を使用する必要があり手続きが煩雑でした。
そこで、行政はこれらの年金記録を10桁の番号に統一させようとしていました。しかし、コンピュータに年金番号があるものの、基礎年金番号に統合・整理されていない記録が約5000万件あることが判明しました。また、過去の紙台帳からコンピュータへの記録の転載が不正確だったことが原因だと指摘されています。この不備は、年金記録が基礎年金番号に正しく統合されず、多くの記録が持ち主不明となる結果を招きました。
この問題は、公的年金制度への信頼を大きく損ない、国民からの批判を集めると同時に行政の情報管理能力に疑問を投げかけることとなりました。
新幹線のぞみ34号台車亀裂事件(2017年)
2017年に起きた新幹線のぞみ34号台車亀裂事件は、博多〜東京行きのJR西日本の新幹線車両の台車で亀裂が発見された事件です。台車の亀裂は14cmにも達しており、あと3cmで台車が破断するという深刻な状態でした。この不備は走行中の異音・異臭が確認されたにもかかわらず、運行を継続したことが原因となっています。
この事件は名古屋駅での床下点検により油漏れが発見され、運転が中止されました。幸い被害者は出ませんでしたが、脱線事故につながる危険性があったと判断され鉄道安全管理の重要性を浮き彫りにしました。
ヒューマンエラーが多い人の4つの特徴
ヒューマンエラーが多い人にはいくつかの共通点があります。例えば、業務中の注意力が散漫な人やストレスや疲労が溜まっている人、社員とのコミュニケーションがきちんと取れていない人が該当します。
ここではヒューマンエラーが多い人にあてはまる4つの特徴について詳しく解説します。

注意力の散漫な人
ヒューマンエラーが多い人の特徴として、注意力が散漫な人が挙げられます。注意力が散漫になる原因として、身体的・精神的不調が考えられます。身体的不調の例として、エネルギー不足や蓄積疲労があります。また、精神的不調の例としては、焦りによるストレスやプレッシャーがあります。
精神的・身体的不調の対策としては、ご飯をしっかり食べたり、睡眠を6時間以上取るといったことに加え、悩みがある時は1人で抱え込まずに周り人に相談し体調を整えることで、業務に集中できるようになるといえるでしょう。
知識や経験が不足している人
業務に対する知識や経験が不足していると、誤った行動を取ってしまうため、ヒューマンエラーを引き起こしてしまいます。特に新入社員は、「上司の業務を邪魔しちゃいけない」という気持ちから相談することをためらう傾向が高いです。そのため分からないことに1人で対処しようとし、結果、誤った行動を取ってしまいます。
この問題を解決するためには、新人社員に対して積極的にコミュニケーションを取り、質問しやすい環境づくりを職場で作り上げることが大切です。
自分の能力や状況判断を過大評価している人
自分の能力や状況判断を過大評価し、自分勝手な判断で業務を進めてしまうと大きなミスや事故に繋がりかねません。特に製造業では業務中に誤った判断をすると、命を落としてしまう可能性があります。
そのため、自分の実力に慢心せずに、周りに危険はないかを意識しながら業務を進めることが大切です。
コミュニケーションが足りていない人
周囲とのコミュニケーションをしっかり取れていない人はヒューマンエラーを起こしやすい傾向にあります。コミュニケーション不足になると、情報共有が不十分となってしまい、認識のずれから誤った行動を取ってしまいます。
特に新しい業務を始める人は、しっかりとコミュニケーションをとり、思い込みで行動することを防ぐ必要があります。そのため、社内でのコミュニケーション促進は組織やチーム全体で取り組むべき重要な問題です。
ヒューマンエラーはなぜ起きる?主な原因
ヒューマンエラーが起こる原因として、人による個人的要因と環境による環境的要因に分けられます。
ここではそれぞれの要因について詳しく解説します。
- 4つの個人的要因
- 5つの環境的要因
4つの個人的要因
確認不足や見落とし等の注意不足
きちんとチェックできていなかったり、見落としといったポカミスが発生するヒューマンエラーのことです。例えば、毎回同じ作業のため、今回も同様であると自己判断し、確認を怠った結果引き起こされるミスになります。
このようなポカミスは、明らかな確認不足や見落としから生じることが多く、発生頻度も高い傾向にあります。
現場改善ラボではポカミスが発生してしまう原因と具体的な対策についてまとめた記事をご用意しております。ぜひご覧ください。
関連記事:製造業でポカミスが起きる原因は?対策の4つの流れを解説
専門家が解説する、より実践的な『ポカミスによるヒューマンエラーを防ぐ方法』を知りたいという方は以下の動画も併せてご活用ください。
慣れによる思い込みや判断ミス
ある程度業務に慣れてくると、マニュアルを把握していることから、少しでも作業を手早く終わらせたいと考える作業者も出てくるかもしれません。業務への慣れが定着すると、作業者の思い込みから判断ミスというヒューマンエラーを引き起こすことがあります。
例えば、一度もミスがないからと最終確認を怠ってしまったり、マニュアルの確認を行わなかった結果、マニュアルの変更に気付かず作業を終えてしまったなどの判断ミスが該当します。意外にもこのミスを起こしやすいのは、ベテラン作業員であるケースが多くあります。
ルールや手順が浸透していない
ルールや手順といった標準が浸透しているはずの現場に浸透していないときに発生するヒューマンエラーです。これには例えば、4M(人/機械/方法/材料)に変更が入るケースや、作業者の慣れにより作業の一部を省略するといった手順不遵守によって多く生じるミスになります。
特にベテラン/中堅作業者が規定を守っていない現場では、OJTによって部下や新人作業者にも影響する恐れがあります。
心身ともに疲労が蓄積している
残業や休日出勤などの長時間労働は、作業者により身体だけでなく精神的にも蝕まれる恐れがあります。特に残業や休日出勤の続く日々は、作業者次第で大変辛いものにもなり得ます。こうした労働を無理して継続してしまう作業者は、後にヒューマンエラーを起こしやすくなります。
例えば、自社の優秀な作業者が突然退職してしまうようなケースにも当てはまります。作業者は表向きの退職理由としてスキルアップなどを挙げたけれども、実は本当は長時間労働から心身に不調を来し退職を選ぶケースも数多くあるのです。
5つの環境要因
教育や訓練が不足している
ベテラン作業者が新人作業者を上手に教育(OJT)できなかった結果、発生するヒューマンエラーです。これにはベテラン作業者が多忙であったり、新入作業者とのコミュニケーションを、日頃からとれていないことが背景にあります。
この問題は中小企業が広く抱える課題です。きちんと教育されなかった新入作業者は、やはり後にヒューマンエラーを起こしやすい傾向にあります。また作業者によっては、そのまま退職してしまうケースも少なくありません。
現場改善ラボでは現場に負担をかけずに効果的なOJTを行う方法について記事内で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事:OJTとは?OFF-JTの違い、負担を減らして効果を出す方法も解説!
業務環境が悪い
毎日勤務する職場だからこそ、円滑な人間関係を築いておくことも重要です。しかし多くの現場で、人間関係のトラブルがあるのも事実です。例えばグループごとに業務を行う際に、作業員同士のコミュニケーション不足から情報の抜け漏れや未共有などのミスが発生すると、それらは後のヒューマンエラーにつながります。
こうした作業員間のコミュニケーション不足などは、作業員の人数が増えるほどに起こりやすくなります。またこのような職場環境をもつ現場では、人間関係の問題だけに留まらず、設備不足や5S活動が徹底されていないなどの問題も抱えていることもあります。
現場改善ラボでは製造業に欠かせない「5S」の概要や順守のための方法について以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
関連記事:5Sとは?意味や活動の目的と効果、ケース別の事例を解説!
また、現場ですぐに実践できる「正しい5S」活動について数々の企業で5S改革を行ってきた、株式会社ヒューマン・ナレッヂの代表取締役である前田 康秀氏が解説した動画を無料で視聴できます。ぜひこちらも併せてご参照ください。
業務で使う機器に不良がある
業務で使う機器に不良があるとヒューマンエラーが発生するリスクが高まります。例えば、生産ラインで使用される機械が故障し正確な部品の供給ができない場合、不完全な製品を組み立てることになり、品質問題を引き起こしてしまいます。
機器の不良はヒューマンエラーと関係ないと思われがちですが、機械を適切にメンテナンスできていれば防げていたかもしれません。機器の不良を防ぐためには、設備保全用のマニュアルや手順書を用意し、従業員に遵守させることが必要です。
現場改善ラボでは設備保全の目的や成功事例について詳しく解説した記事をご用意しております。併せてご覧ください。
関連記事:設備保全とは?種類と考え方、取り組む重要性や事例を解説!
設備保全においてよくある課題が『属人化』です。設備保全の属人化を防ぐ方法について、専門家が解説する動画も無料でご覧いただけますので、こちらも併せてご活用ください。
コミュニケーションが取りにくい雰囲気である
現場でのコミュニケーションが取りにくい雰囲気であると、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。コミュニケーションがとりにくい雰囲気では情報共有や意思疎通が十分に行われず、作業者やチームメンバー間での誤解が生じます。お互いを誤解したままでいる状況は誤った行動につながりやすく、ヒューマンエラーを引き起こしてしまいます。
コミュニケーションが取りにくい雰囲気は、組織の文化やチーム内の関係性に影響されます。特に、若手の意見が尊重されない、または情報共有が制限されるような環境では、作業者はコミュニケーションを取るのを躊躇ってしまいます。したがって、組織やチーム内でのオープンなコミュニケーションと情報共有の促進が重要です。
安全への取り組みが不十分である
安全への取り組みが不十分である環境では、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。安全への取り組みが不十分である場合、作業者は作業手順や規制を無視して作業を急いだり手順書を読まずに機械を触ってしまう可能性があります。これにより事故やケガのリスクが増大し、ヒューマンエラーの発生に繋がります。
安全への取り組みが不十分な環境では、作業者が安全に関する情報やトレーニングを受ける機械が不足している可能性があります。こうした環境では、作業者は安全を無視したり、リスクを過小評価する傾向が高lまり、それがヒューマンエラーを引き起こす可能性があります。したがって、組織全体で安全への取り組みを積極的に促進し、作業環境の安全性を確保する努力をする必要があります。
従業員の安全意識を高めるためには教育が不可欠です。安全教育の実施方法については、以下の記事で基礎的な内容をご確認いただけます。
ヒューマンエラーを防止するための8つの方法
上記で述べたように、ヒューマンエラーは個人的要因と環境的要因によって引き起こされます。ここではヒューマンエラーを防止するための方法として以下8つを解説します。ヒューマンエラーの防止策を学び、現場の改善に活かしましょう。

本記事と併せて以下の動画もご活用いただくと、自社におけるヒューマンエラーの原因分析に基づいて、効果的な対策方法を考えていただくことが可能です。ぜひこの機会に、専門家による解説動画もご覧ください。
エラーが多い業務の見直し/効率化を行う
日頃よりエラーの多い業務は、定期的に見直しを行ったり、効率化を図れるようマニュアルのプロセスやルールを見直す必要があります。その中で不要であると複数の作業者が思う業務は、思い切って削ってしまうことも1つの方法です。
該当する業務を削れば、そもそもエラーが発生することもありません。もちろん必要な箇所には追加を行い、不要な箇所を思い切って削ることにより、効率化の推進にも寄与します。
このような工程における不要な箇所を「ムダ」と捉え、徹底的に排除したのがトヨタ生産方式における7つのムダの考え方です。トヨタ生産方式と7つのムダに関する、より具体的な概要は以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
・関連記事:トヨタ生産方式(TPS)をわかりやすく解説!7つのムダ、メリットやデメリットとは?
・関連記事:【トヨタ式】7つのムダとは?具体例を交えてムダを解説
トヨタ生産方式に基づいた現場改善の視点について、世界各国のトヨタ関連会社の経営に携わり、トヨタの現場を見てきた小森 治氏が解説する動画も併せてご活用ください。
エラーが起きない工夫をする(フールプルーフ)
エラーを起きにくくすることは、ヒューマンエラーを発生させないように工夫を施すことでもあります。この工夫を施すことをフールプルーフともいいます。
具体的な工夫として、複数同時にログイン不可の仕組みを取り入れたり、入力ミスでエラー表示がなされるなどの工夫などが該当します。こうした仕組みを取り入れると、そもそもエラーが起きることもありません。そのため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができるのです。
ヒューマンエラーを発生させない仕組みとして代表的な「フールプルーフ」について、現場改善ラボでは詳しく解説した記事をご用意しております。併せてご覧ください。
関連記事:フールプルーフとはどういう設計?品質不良/ヒューマンエラーを未然防止する考え方、使用例を解説
危険な業務は自動化する
業務の内容によっては時に危険を伴うことがあります。このような危険業務については人を活用せず、システムに頼り自動化させることが効果的です。
例えば、ヒューマンエラーが発生し作業者にケガをさせる危険性のあるような業務は、出来る限り自動化することで安全性を高められます。また、システムによる作業の為、ヒューマンエラーも解消できます。
複雑な業務を分かりやすくする
プロセスが複雑な業務の際には、ヒューマンエラーが起こりやすくなります。このような業務を行う場合には、業務フローを出来る限り分かりやすくすることが求められます。
この対策として適切なものに、マニュアルを作成することが該当します。マニュアルを作成すると、その通りに作業を進めれば良いため、結果としてヒューマンエラーを効果的に削減できます。
またこの他に、定期的に研修や勉強会の場を設けることも有益です。例えば作業者には事前に業務フローに関するマニュアルを確認してもらい、ある程度の内容を把握しておいてもらうことで、その後スムーズに業務に取り組みやすいでしょう。
ただ、やみくもにマニュアルを作成しても、現場で活用されなくては意味がありません。以下の記事では、現場で活用されるマニュアルを作成するポイントを解説しています。
関連記事:マニュアルの意味とは?わかりやすく作るコツと流れを解説
ヒヤリハットの報告や共有を徹底する
今回は未然に防ぐことはできたけれども、大きなトラブルにつながり兼ねなかった出来事のことを、ヒヤリハットといいます。このヒヤリハットは、作業中にヒヤリとした出来事や、ハッとした出来事が該当します。
例えば、会議時間を勘違いしあと少し遅れていれば遅刻していた・クライアントへの電話を他のクライアントと間違えそうになったなどの事例などがこれに当てはまります。もしヒヤリハットを起こしてしまったとしても、慌てずに落ち着いて対処し、報告や共有を徹底することが重要になります。
ヒヤリハットの概要や報告書の書き方については以下の記事でも詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
関連記事:ヒヤリハットの意味は?報告書の書き方や業界別事例集を解説!
ヒヤリハットに基づいた安全対策の進め方については、以下の専門家による解説動画もご活用ください。
安全に関する教育を定期的に行う(KY活動)
KY活動とは危険予知活動の略称で、安全についての教育を定期的に行う活動のことをいいます。具体的には、作業を始める前に作業への危険性や、危険箇所に対し話し合いを行います。そして、話し合いの後に対策や目的を定めて呼称設定をし、指差し呼称で安全衛生を先取りしながら作業を進める活動のことを指します。
関連記事:KY活動(危険予知活動)はなぜ必要?進め方や活動内容の例、記録方法は?
指差し呼称のやり方に関しては、厚生労働省のKY活動に関する資料に掲載されています。
(2)指差し呼称のやり方
練習では、指差し呼称の基本形を次のとおり徹底して身につけます。
目は・・・
確認すべき対象を、しっかり見る。
腕・指は・・・
左手は親指が後ろになるようにして手のひらを腰にあてる。右腕を伸ばし、右手人指し指で対象を差す。「○○」のあとで、いったん耳元まで振り上げて、本当に良いかを考えて確かめた上で、「ヨシ!」で振り下ろす。右手は、縦拳(親指を中指の上にかけ、握りの渦巻きを天井に向ける)から人差し指を伸ばす形をとる。
(※左利きの人は、その逆で行う。 )
口は・・・
はっきりした声で、「○○ヨシ!」、「スイッチ・オンヨシ!」「バルブ 開ヨシ!」と唱える。
耳は・・・
自分の声を聞く。目、腕、口、指を総動員し、自分の作業行動や対象物の状態を確認する手段です。
【引用:厚生労働省『第3章 KY活動』】
職場環境の課題を改善する
職場の人間関係などの課題がある際に、その課題を改善することにより、ヒューマンエラーも改善される可能性が高いでしょう。例えば、ベテラン作業者と部下の間で、情報共有や連絡事項の報告などがスムーズにいっていないケースには、コミュニケーション不足などの課題が背景にあるはずです。そのため、出来る限り多くのコミュニケーションをお互いにとることが求められます。
この課題では、ベテラン作業者から部下へと積極的なコミュニケーションをとることにより、改善されやすい傾向にあります。
事故を未然防止するためのKY活動の進め方について、元労働基準監督署署長の村木 宏吉氏が解説している動画も併せてご活用ください。
いつでも確認/学べるようにマニュアルを整備する
ヒューマンエラーを防ぐためには、常時確認することが必須であると言えます。どのような業務を進めるにしても、とにかく確認を怠らないようにしましょう。また、マニュアルを整備することも効果的です。
マニュアルの整備とは、これまで使用していたマニュアルを定期的に更新したり変更し、新たに付け加えたり不要な箇所は削除をするなどしてマニュアルそのものを整えることを指します。この整備を行うことにより、自社のルールをより強固なものにしたり、徹底させるために役立ちます。
注意点として、マニュアルを更新・変更した際は、作業員にも周知をするという点が挙げられます。
ヒューマンエラー防止のマニュアルに適するのは紙?動画?
厚生労働省のヒューマンエラーに関する資料によると、ヒューマンエラーを防ぐ方法について、以下の方策を公表しています。
ヒューマンエラーの防止は難しいのですが次のような方策を採ります。
1)人が間違えないように人を訓練する。
2)人が間違えにくい仕組み・やりかたにする。
3)人が間違えてもすぐ発見できるようにする。
4)人が間違えてもその影響を少なくなるようにする。
人が行うのですから、どんなに人を訓練しても間違いは避けられません。人間は適度な緊張のときにはエラーの発生は少ないのですが、過度の緊張や緊張感が少なすぎるとエラーが多く発生します。また単調な監視業務では30分を超えると緊張が続きません。
ヒューマンエラーは原因ではなく結果であると考えると納得出来るのではないでしょうか。こうした人間の特性を知りながら人の持つ柔軟性などの長所を活かす工夫が求められます。
【引用:厚生労働省『職場のあんぜんサイト:ヒューマンエラー』】
上記の方策や人の特性や長所を活かす工夫には、適切なマニュアルの作成が不可欠です。マニュアルには紙マニュアルと動画マニュアルがありますが、動画マニュアルの方が最適です。
マニュアルには動画がおすすめな理由
紙マニュアルよりも動画マニュアルの方がおすすめな理由として、複雑な作業でも「目で見て学ぶ」ことができる点です。
特に、危険を伴う業務やエラーを繰り返してしまうような作業に関するマニュアルには、視覚的に誰でも理解でき、かつ大切なポイントをダイレクトに伝えられる動画の活用が最も効果的だといえます。
視覚と聴覚の両面から訴求可能な動画には、文字だけの静止画よりも短時間かつ大量の情報を伝達できるというメリットがあります。一般的に、動画の情報量は文字の5,000倍ともいわれています。
また、現場作業は動的であるため、作業内容を正しく理解してもらうには一連の流れを理解することのできる動画の方が望ましいです。動画マニュアルであれば作業の動きを可視化することができるため、文字や写真では伝わりづらい微妙なカンコツといった内容を直感的に理解することができます。
おすすめな動画マニュアル「tebiki」とは
動画マニュアルは、YouTubeで作成する他にも様々な動画マニュアルサービスを使って作ることができますが、最もおすすめしたい動画マニュアルサービスは「tebiki」です。
【YouTube設置】
tebikiは普段のOJTをスマートフォンで撮影することで誰でも簡単に動画マニュアルを作成できることが特徴です。動画編集の知識がなくても簡単に作れることに加え、字幕や翻訳も自動生成される仕組みが備わっています。特に、翻訳機能は100ヵ国以上を超える言語に対応しているため、外国人スタッフの教育場面にも使用可能です。
また、動画のアップロードや字幕の編集、写真の挿入なども簡単に行うことができるため、動画編集の経験がない人でも直感的に作成することができます。機能がシンプルなため、誰が作っても標準的なマニュアルを作成することができます。
さらに、tebikiには管理者側のメリットとして習熟度管理機能があり、誰が/いつ/どれくらいマニュアルを見たか、業務ができるようになったかをグラフで可視化することができます。そのため、ヒューマンエラーが発生した際の原因を特定しやすくなり、ミスの再発防止にも繋がります。
tebikiの概要や実際に導入している企業の事例、動画マニュアル作成のコツについてまとめた資料を以下の画像から無料でダウンロードできます。是非ご覧ください。
動画マニュアルtebikiを使ってヒューマンエラー対策を行っている具体例
上記でご説明したように、ヒューマンエラー対策には動画マニュアルの活用がおすすめです。動画マニュアルを使うことで、作業内容や業務中の危険要因を正しく認識できるようになり、ヒューマンエラーの発生を減らすことができます。
特に動画マニュアルtebikiは誰でも簡単に動画マニュアルを作成することができるため、標準的なマニュアルを早く展開することが可能です。ここでは、動画マニュアルtebikiを使ってヒューマンエラー対策を行っている企業事例を2つ紹介します。
大同工業株式会社
大同工業株式会社は1933年に自転車チェーンの製造会社として創業して以来、オートバイ、自動車、産業機械、福祉機器といった領域へ積極的に事業展開を行い、現在では海外11カ国に拠点を持つグローバル企業です。
以前、大同工業株式会社は新人教育においてOJTで学ぶことが非常に多く、トレーナーの知識や経験、指導方法によって教育のバラつきが発生していました。担当者によって業務のコツやポイントに差があり、それゆえに業務手順が異なるという我流化が発生していました。最初は小さな我流化だったにもかかわらず、それが2世代、3世代と受け継がれることで大きな我流化となり、試験におけるヒヤリハットの発生や評価結果のエラーによる再試験などの手戻りの一因となっていました。
そこで大同工業株式会社はtebikiを導入しました。まず動画マニュアルの作成にあたり、使用頻度の多い特定機種をリストアップし、一年間の作成スケジュールを立てました。またマニュアル作成の過程はできるだけオープンにし、社員全員が作成に携わりました。大同工業株式会社では、作成したマニュアルを作業現場にあるタブレット端末で視聴できるようにしています。今ではマニュアルをQRコードに変換して、逐一検索をかけずに視聴できる仕組みを整えています。
大同工業株式会社はtebikiを導入したことによって、部内全体で標準化を行うことができ、部内で発生していた試験中のヒヤリハットや評価エラーを削減することができました。また、マニュアル作成時にメンバー全員に回覧したことで、個人のカンやポイントが出てきて、業務の効率化・最適化も達成することができました。
参照元:製造業の技術部門の業務を動画で標準化。教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。
株式会社ジェイ・メイト
株式会社ジェイ・メイトはスーパーの店舗配送を行う物流センターで、メーカーから届いた商品を受け入れて、配送店舗別に各商品を仕分ける作業を行っています。現場は24時間365日稼働しており、ベトナム人を中心とした多くの外国人も働いています。
24時間稼働の物流センターであるため、トレーナーと新人のシフトがあわない、外国人スタッフに言葉が通じない、教える人によって内容が違うなどの理由で、人的な仕分けミスを減らすための教育が十分にできていないことが課題でした。
そこで株式会社ジェイ・メイトはtebkiを導入し、仕分けミスをしてしまう間違った手順と正しい手順を撮影し、動画マニュアルとして運用しています。また、外国人スタッフには自動翻訳された字幕を見せています。スタッフ全員に動画を見せた後に、仕分けミスが起きる都度、ミスした人に現場でタブレット端末で動画を見せて再教育する、ということをやったところ、1ヶ月目あたりから大きくミス発生率が下がり、ヒューマンエラーを半減させることができました。
参照元:効率よく再教育することで、倉庫内作業の仕分けミスが半減!
ヒューマンエラーを効率的に防ぐポイントとは?
マニュアルを活用することで、作業内容をいつでも確認・学習することができるため、業務の理解不足によるヒューマンエラーを防ぐことができます。また、動画マニュアルtebikiを活用することで、より効果的なマニュアル運用が可能になります。
ここでは、ヒューマンエラーを効率的に防ぐ以下の4つのポイントについて詳しく解説します。

ヒューマンエラーはゼロにできないことを理解する
残念ながらヒューマンエラーを完全に無くすことは不可能です。なぜなら、人はどれだけ注意していても誤った判断を下したり、覚えたことを忘れてしまう生き物だからです。しかし、ヒューマンエラーはゼロにできないことを理解しきちんとした対策を講じることで、ミスが起きてしまったとしても適切に対処することが可能になり、リスクを最小限に抑えることができます。
ヒューマンエラーはゼロにできないからこそ、リスクを減らすための対策を講じることが必要です。トレーニングやシステムの改善、環境の整備などの対策を行い、リスクを最小限に抑えることが大切です。
事前に作業の危険性を想定するためには、リスクアセスメントを行うことが効果的です。リスクアセスメントの進め方については以下の記事か動画をご覧ください。
関連記事:リスクアセスメントの目的や進め方は?専門家の解説を交えてわかりやすくご紹介
ヒューマンエラーの要因を考える
ヒューマンエラーの要因を考えることは、同じエラーを繰り返さないための重要なポイントです。要因を明らかにし、それに対する対策を講じることで、ヒューマンエラーの再発を効果的に防止することが可能です。
ヒューマンエラーは認知的負荷やストレス、作業環境の問題、不適切な手順や訓練不足などさまざまな要因によって引き起こされます。ヒューマンエラーが発生した際は原因を特定し、要因を分析することで同じエラーが再発する可能性を低減することができます。
ヒューマンエラーの要因を洗い出すことで、一番のボトルネックとなる真因を明らかにすることができます。ヒューマンエラーの要因や真因を特定するためには『なぜなぜ分析』が効果的です。なぜなぜ分析の進め方については以下の記事か、トヨタ社内の専任講師が解説する動画をご覧ください。
関連記事:改善につなげる『なぜなぜ分析の進め方』は?鉄則や落とし穴、事例を解説!
ヒューマンエラーをリスト化して1つ1つ対策をする
ヒューマンエラーをリスト化することで、個々のヒューマンエラーに対して抜け漏れなく対処することができます。リスト化されたヒューマンエラーを丁寧に検証し、それぞれの要因に対する対策を確実に行うことで、抜けもれなくヒューマンエラーを防止することができます。
ヒューマンエラーをリスト化する際には、個々のエラーを詳細に記録し、それぞれの要因を明確に把握します。その後、要因に対する対策を丁寧に検討し、実施することで、抜け漏れなくヒューマンエラーを防止することができます。
動画マニュアルを活用して対策する
動画マニュアルを活用し、作業内容を可視化することによってヒューマンエラーの発生を効果的に防ぐことができます。動画マニュアルは視覚的に訴求できるため、作業者の理解を促進します。また、正しい手順や操作方法を見て学ぶことで、誤解や勘違いを防ぎ、ヒューマンエラーを減少させることができます。
動画マニュアルを作成する際に気を付けるポイントは、短いものを複数作成することです。1時間の動画マニュアルになるとどこを確認したら良いか分からなくなり、結果として使われなくなります。
しかし、一連の作業ではなく作業ごとに区切ったマニュアルを作成すると、業務内容を区切りながら理解することができるため、「どこまでが分かっていて、どこからが分からないのか」が明確になります。そのため、動画マニュアルを作成する際は1つの動画を5分以内に収めるように意識しましょう。
動画マニュアルtebikiは、動画アップロード本数が無制限であるため何本でも作成することができ、マニュアルの大量作成に最適です。導入企業の中には一年間で1,300本ものマニュアルを作成した企業事例もあります。
tebikiのサービス資料は下記の画像から無料でダウンロードできます。動画マニュアルtebikiを活用してヒューマンエラーを効果的に防ぎましょう。
ヒューマンエラーに関するQ&A
ヒューマンエラーを起こしやすいものは何ですか?
ヒューマンエラーの発生は個人的な問題よりも作業環境における5Sの欠陥やコミュニケーションが取りづらい雰囲気といった環境的要因に強く作用されます。例えば、作業場が乱雑で整理されておらず、必要な道具や資料が見つからない場合、作業者は業務に集中できなくなり、ミスや事故が起きやすくなります。また、コミュニケーションが取りづらい雰囲気では情報共有が不十分になり、誤った行動を取ってしまいがちです。
こうした環境的要因は組織全体で改善すべき重要な課題です。作業手順書を作成したり、管理職やリーダーシップが従業員と積極的にコミュニケーションを取ることで、組織全体の作業環境が改善され、ヒューマンエラーの削減に繋がります。
ヒューマンエラーを防ぐには限界がある?
人は注意して作業に取り組んでいても、ミスをする確率が1000分の3あると言われています。さらにそのミスに気づかず、見落としてしまう確率が1000分の3あり、これらをかけ合わせた100万分の9がヒューマンエラーの限界であると言われています。そのため、ヒューマンエラーを完全に無くすことは不可能であると言われています。
しかし、多くの会社では100万分の9までミスの発生を防ぐことができておらず、まだまだ改善の予知があります。
ミスを減らすためには、ミスの発生原因となる環境やしくみを見直し、改善し続けることが大切です。
まとめ
ヒューマンエラーはストレスや疲労、思い込み、5Sの不十分、コミュニケーション不足などさまざまな要因によって引き起こされます。そのため、ヒューマンエラーを防ぐには、ミスが起きた要因を特定し、それに対して適切に対処することが重要です。
ヒューマンエラーを防止するための方法として以下8つを紹介しました。
・エラーが多い業務の見直し/効率化を行う
・エラーが起きない工夫をする(フールプルーフ)
・危険な業務は自動化する
・複雑な業務を分かりやすくする
・ヒヤリハットの報告や共有を徹底する
・安全に関する教育を定期的に行う(KY活用)
・職場環境の課題を改善する
・いつでも確認/学べるようにマニュアルを整備する
特にヒューマンエラーを防ぐにはマニュアルの整備が重要です。マニュアルは作業の手順を教えるためのものですが、内容が更新されていないと作業者は誤った行動を取ってしまいミスにつながります。そのため、定期的にマニュアルの確認を行いましょう。
またマニュアルを動画化すると、現場の動きを可視化できるため、文字や写真では伝わりづらい作業内容を正しく理解してもらうことでヒューマンエラーを削減することができます。動画マニュアルtebikiを導入した大同工業株式会社や株式会社ジェイメイトはtebikiを活用することで、ヒューマンエラーの削減を達成しています。
この記事で紹介した動画マニュアルtebikiの資料は無料でダウンロード可能です。ぜひこの機会に、ヒューマンエラーの削減を実現するためにtebikiの資料を無料でダウンロードしてみませんか?